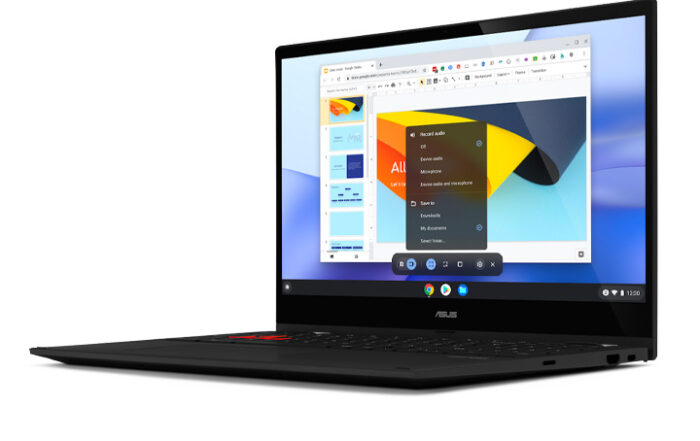社員インタビューを公開しました(Vol.6:地方創生担当)
入社2年目、持ち前の向上心と素直さ、そしてコミュニケーション能力で 日夜アイランドコネクト沖縄の在宅ワーカーを支える、若手 地方創生担当者のインタビューを公開しました。ぜひご覧ください。 https://boo-oki.com/interview-shinzato/
八重山毎日新聞に掲載!
・八重山毎日新聞2015年09月20日 社会・経済 2015年シルバーウィーク期間中(9月19日~9月23日)、当社のプロジェクト事務局の崎山が石垣港離島ターミナルへ訪れる観光客を対象に、移住についてのアンケートを実施しました。大型連休だったこともあり、離島ターミナルを利用する多くの観光方々にアンケートを記入いただけました。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 アンケート内容は、竹富町への移住の有無、移住を検討するに置いての情報や就業形態などについての選択式でした。なお、アンケートを実施しながら、移住応援プロジェクトとして窓口の紹介も行っておりました。これからアンケート調査を集計し、調査結果を踏まえて竹富町への移住への取り組みへ反映していきたいと思います。 総務省案件「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」とは、沖縄県八重山郡竹富町への移住希望者を対象とし、民間在宅テレワーカーの育成研修を実施後、「在宅レテワーカー」として就業環境を提供する地域実証事業です。 【お問い合わせ】 竹富町移住応援プロジェクト事務局 担当者:宇良(うら) TEL :070-5271-9824 E-mail :iju@boo-oki.com 営業時間 9:00~17:00 月曜~金曜(日と祝日を除く) ・総務省案件「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」
沖縄県内学校教育用向け、大規模PC機器展開作業支援を受注しました。
■作業概略(某市内 中学校6校) ① PC教室: SV(1台)、PC41台(先生機1台、生徒機40台、NW・アプリケーション設定) ※ 6校台数・アプリ設定共通、NWは同一ポリシー、IP値は各校相違 ② 新規ノートPC(52台/2校)、既存校務用PC設定変更: 新L3スイッチ導入に伴いPCのNW設定変更、ウイルスソフトの製品変更 ③ LAN配線、L3設定
kintone(キントーン)のデベロッパーパートナーに加入しました。
kintone(キントーン)は、サイボウズ社が提供している 業務効率化のためのクラウドサービスです。 kintone ホームページ https://kintone.cybozu.co.jp/ Webブラウザ上で簡単に(ドラッグ&ドロップで)フォーム画面を 作成することができたり、また、簡単に部署やチームのメンバーと データを共有することができます。 さらに、フォームとデータベースを組み合わせるだけでなく、 ワークフローや権限管理、アラートといった、 日常業務で嬉しい「かゆいところに手が届く」機能が搭載されています。 こうした機能を組み合わせながら、オリジナルの業務アプリを 安価に作成することができます。また、クラウドサービスのため、 ユーザーがわざわざサーバーを用意する必要もありません。 弊社では同ツールを使った開発・保守サービスをご提供しております。 ぜひお気軽にご相談ください。
那覇市教育委員会様のデータ移行業務を自動化し、短納期で実施完了
弊社はこのたび、那覇市教育委員会様における沖縄県生徒情報管理システムからのデータ移行業務をプログラム化することで、短納期での実施を完了いたしました。 この実績を元に、弊社は今後スズキ校務支援システムへのデータ移行業務を弊社のサービスとしてパッケージ化し、お客様のニーズにお応えしてまいる所存です。 <参考リンク> 那覇市教育委員会様のプライベートクラウド上にスズキ教育ソフト社製「スズキ校務シリーズ」の構築を完了 https://boo-oki.com/naha-edu-suzuki/
弊社ニアショア開発サービスのご案内
このたび新たに弊社のニアショア開発サービスに関するページを設けました。 ブルー・オーシャン沖縄のニアショア開発サービス https://boo-oki.com/system-dev/ 弊社では、IoT系一部上場企業出身エンジニアやバイリンガルエンジニアなど平均業務経験15年以上の開発者を擁し、各種システムのニアショア開発に関するご相談を承っております。また、設計、構築、さらに稼働後の運用まで、幅広く対応しております。 豊富な経験に裏付けられた高品質なニアショア開発サービスをお探しのお客様はぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。