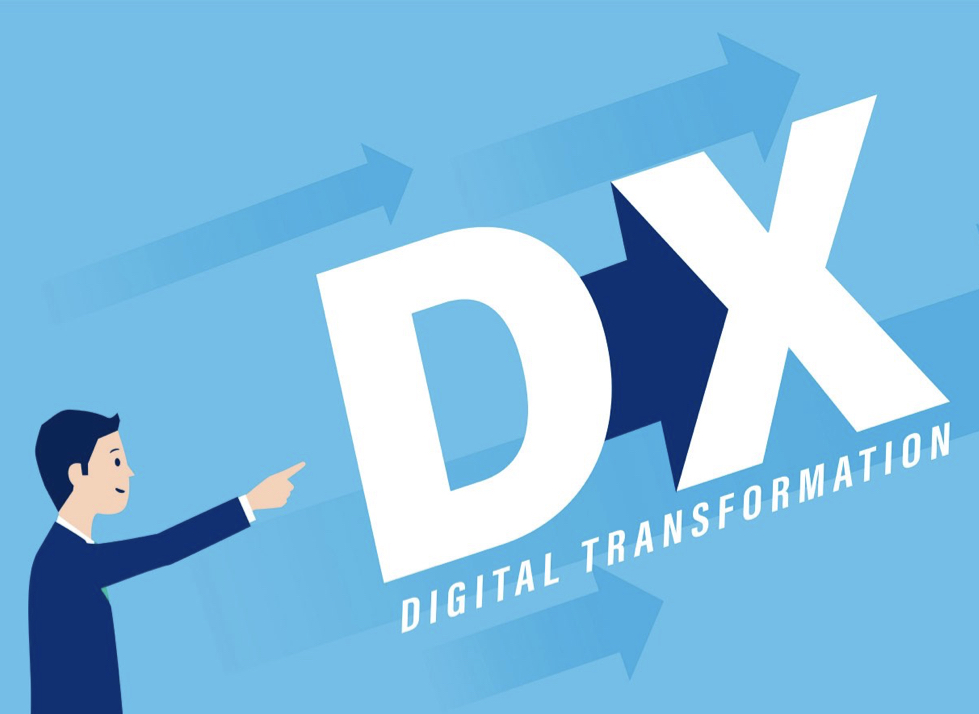株式会社アプトジャパン様と販売パートナー契約を締結、
同社が「グラスフォン」の取り扱いを開始
弊社はこのたび株式会社アプトジャパン様(所在地:宮城県名取市、以下アプトジャパン様)と販売パートナー契約を締結いたしました。またこれに併せて、アプトジャパン様による弊社の防災DXソリューション「グラスフォン」の販売取り扱いがスタートしました。 アプトジャパン様はこれまでネットワークセキュリティおよびテレワークソリューションを強みとした事業を展開されておりました。アプトジャパン様は今回、新たにグラスフォンを軸とした防災IT事業を立ち上げることで、東北や北海道のお客さまの防災対策・共助強化を推進し、同地域での災害による被害を減らしたい、という思いを持っています。 【関連記事】APTJAPAN新規事業のお知らせ なお、弊社グラスフォンは引き続き広く販売パートナー様を募集しておりますので、ご関心をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
横浜市会 新たな都市活力推進特別委員会の議員の皆様が当社シェアオフィスを行政視察
当社が竹富町・西表島で運営するシェアオフィス「The Blue Office -IRIOMOTE-」に、このたび横浜市会(市議会)「新たな都市活力推進特別委員会」の議員の皆様が行政視察にいらっしゃいました。 【「新たな都市活力推進特別委員会」の取り組みについて】 オープンイノベーション等による企業支援や誘致促進、グローバル都市の実現、文化芸術創造都市や観光MICEの推進等に関することを命題として調査研究を行っており、今年度は都市の魅力を高めるための「人」や「企業」への支援等がテーマとなっています。 当委員会の実績等はこちらをご覧下さい 視察当日は当社シェアオフィス事業におけるこれまでの経緯や実績、テレワークやワーケーションでの活用のされ方、また、当社が現在行政と共同で実施しているテレワーク事業や行政に期待する支援等について、約1時間という限られた時間の中、ご説明および議員の皆さまとのディスカッションをさせて頂きました。また、今回の行政視察について、後日改めてお礼状も頂戴いたしました。 当社では今後も離島におけるシェアオフィスの運営を通じ、テレワークやワーケーションといった新しい働き方を多角的かつ継続的にサポートしてまいります。
防災ソリューション「Grasphone(グラスフォン) for防災」沖縄県石垣市への導入が決定しました
このたび弊社の防災ソリューション「Grasphone(グラスフォン)for防災」の石垣市への導入が決定いたしました。 詳細は以下のページをご覧ください。 安否確認・共助強化ソリューション「Grasphone(グラスフォン) for防災」、沖縄県石垣市への導入が決定
2019年度竹富町民等船賃負担軽減事業に係る管理システム導入委託業務を受託
当社はこのたび、2019年度竹富町民等船賃負担軽減事業に係る管理システム導入委託業務を受託いたしました。 竹富町では沖縄振興特別推進交付金を活用した離島住民割引を実施しています。これまでは、住民が船舶割引を受ける場合、船舶チケット購入カウンターで割引運賃カードを提示し、申請用紙に記載をする必要がありました。 さらに、船舶会社は申請用紙をカウントし手入力で帳票に書き込む作業が発生していました。 本事業においては、住民カードへQRコードを貼り付け、船舶チケット購入カウンターに設置されたQRコードリーダーで読み込むことで用紙記入の手間を省きます。 さらに、船舶会社にてこれまで手作業で行われていた用紙のカウントと入力業務がなくなることで、管理業務の効率化を図れるという事業となります。 ※7月中旬からサービス開始予定です。
沖縄県うるま市の「テレワーク人材育成事業」を受託しました
このたび弊社は昨年度に続き沖縄県うるま市「テレワーク人材育成事業」の受託事業者として選定されました。 新たにうるま市のテレワーカー150名の育成および事業斡旋を行ってまいります。 本事業の概要はうるま市のホームページをご覧ください。 【参考リンク】 テレワーカーを募集します!(うるま市ホームページ) https://www.city.uruma.lg.jp/sp/sangyou/150/22213
【地方創生コラム】地域DX推進と沖縄のテレワーク人材
こんにちは、地方創生担当の安田です。今日は、今年度からアイランドコネクト沖縄で始まった「地域DX人材育成」カリキュラムについてお話したいと思います。 新たに「地域DX人材育成」カリキュラムを開始 弊社では現在「アイランドコネクト沖縄」の取り組みにて、700名以上の沖縄在住テレワーカーを育成・業務斡旋しています。 育成に関してはこれまでWebライティングやアノテーション(AI分野)を中心に実施。また、業務斡旋についてはこれら2業種以外にも、Webサイトの制作や運営、経理事務、SNS運用代行など多岐に渡る分野で実施されています。 そんな中、今年度より新たに2つの育成研修カリキュラムが追加されました。ひとつが「地域DX人材育成」、もうひとつが「動画編集人材育成」です。 ここでは「地域DX人材育成(※)」について、私たちの思いなどをお伝えしたい次第です。 ※研修プログラム監修:国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 主幹研究員/沖縄地域統括長 新谷隆 なぜ私たちのDX推進サービス? いま世の中では、経済産業省の強力なリーダーシップの下でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されており、また、数多くの企業がさまざまなDX化支援サービスを提供しています。 そんな中、私たちアイランドコネクト沖縄も今年度からDX推進人材の育成をスタートしました。現在、第1次募集に手を上げた約60名が研修に参加しています。 私たちのDXの取り組みにはいくつか特徴的な部分がありますので、順を追ってご説明したいと思います。 1.単なるIT活用ではないDXの実現 DXとIT活用はその意味において大きく異なります。私たちは単に業務の効率化を目指すIT活用ではなく、業務における本質的な課題解決による「新しい価値の創出」をDXと定義し、その推進を担える人材の育成をアイランドコネクト沖縄で行っています。もちろんその取り組みにおいてITは活用するのですが、IT活用はあくまでも手段であり、DXの真の目的は新しい価値の創出にあると捉えています。 2.ベンダーのしがらみがないDX推進 IT企業によるDX支援サービスでときおり目にするのが「ベンダーのしがらみ」です。つまり、そのIT企業と近い関係にあるメーカーの商品を導入することが避けられないケースですが、真のDXを目指すのであればベンダーの影響はできるだけ少ない方が望ましいでしょう。私たちはそのようなしがらみが一切ない環境・立場から、お客さまの真のDXを推進します。 3.豊富なDX経験を基にしたスタッフ育成 DXという言葉が一般化したのはごく最近のことですが、「業務の本質的な課題解決による新しい価値の創造」という理解において、弊社では2015年から沖縄県内の自治体と組み、さまざまなDXを継続的に行ってまいりました。これらの実務で積み上げられた独自のノウハウを基に、アイランドコネクト沖縄に所属するテレワーカー向けにオリジナルのDX人材育成カリキュラムを提供しています。 4.地域完全密着型のDX 私たちの場合、「地域DX」とあるとおり、対象となるお客さまは沖縄県内企業、またDXをご支援する当方担当者(=地域のテレワーカー)も全員沖縄在住です。従って、あらかじめ地域の状況や環境を充分に理解した上でお客さまの課題を自分事とし、かつDX専門家の見地からヒアリング〜新しい価値の創出に至るご支援をさせていただくことが可能です。 5.お客さまの新たなCSRスタイルとして いまは企業の社会的責任が問われる時代となっており、それを受けてさまざまなCSR活動が行われています。 もともとアイランドコネクト沖縄は「就業環境が極めて限られる沖縄の離島の人々に副収入の手段を提供したい」という弊社メンバーの思いからスタートしました。現在では700名以上のテレワーカーがアイランドコネクト沖縄に所属、毎月さまざまな手段で副収入を得ています。業務をご発注頂いているお客さまは在京企業から沖縄県内企業まで多種多様ですが、実はアイランドコネクト沖縄に業務をご発注頂くこと自体がまさにCSR活動となっており、結果、離島をはじめ沖縄県内の各地域で暮らす人々の生活に大きなプラスの影響をもたらしています。 真のDXで沖縄を変えていきたい このように、私たちがアイランドコネクト沖縄を通じて沖縄の各地域に密着したDX人材を育成することには、とても大きな意味があると考えています。 お客さまにおかれましても、貴社のさらなる発展のトリガーとして、またCSRへの取り組みとして、ぜひアイランドコネクトの地域DX人材をご活用頂きますよう、ご検討の程よろしくお願いいたします。